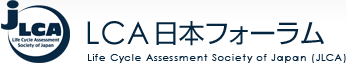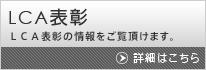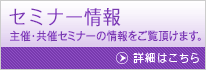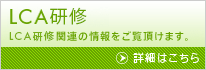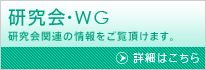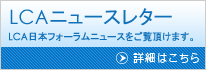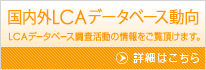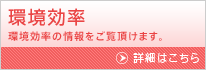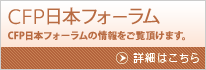- HOME
- > セミナー情報
セミナー情報(各講演資料は、「会員専用ページ」よりご覧ください。)
過去のセミナー一覧
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|
| 2026.01.30 LCA日本フォーラム主催:国際動向セミナー |
<開催概要> 今年度のLCA日本フォーラムの国際動向セミナーでは、昨年10月に開催されたTC207トロント総会を中心にLCAに関連する最新の動向についてご紹介いただき、フォーラム会員様を中心に140名を超える方にご参加いただきました。 開催日時:2026年1月30日(金)15:00-16:40 開催形式:オンライン(Zoomウェビナー) 主 催:LCA日本フォーラム 共 催:日本LCA学会 |
||
| 「TC207 全体会合(トロント)の報告」 | 経済産業省 イノベーション・環境局 国際標準課 | 海沼 遼平 | |
| 「マスバランスモデル関連規格の動向:14021(自己宣言)と14077(COC for LCA)」 | 一般社団法人日本LCA推進機構 理事長 ISO/TC207/SC3及びSC5対応国内委員会 委員長 |
稲葉 敦 | |
| 「ISO/GHGP連携によるGHGアカウンティング規格改訂の動向」 | 一般財団法人 日本エネルギー経済研究所 理事 ISO/TC207/SC7対応国内委員会 委員長 |
工藤 拓毅 | |
| 「TC207の今後について」 | 東京大学大学院工学系研究科 教授 環境管理規格審議委員会 委員長 |
松橋 隆治 | |
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|
| 2026.01.19 第22回 LCA日本フォーラム表彰 記念講演会(奨励賞受賞含む) |
<開催概要> 2026年1月19日(月)14時00分より、令和6年度「第22回LCA日本フォーラム表彰 表彰式・記念講演」が海運クラブ(東京千代田区)にて開催されました。10件の受賞企業様および1名の功労者様に各賞の賞状および副賞が授与されました。 表彰式に引き続き、受賞者の表彰記念講演が行なわれ、フォーラム会員を中心に約120名の皆様にご参加頂き、盛況に開催されました。 開催日時:2026年1月19日(月) 14:00-15:30 第22回 LCA日本フォーラム表彰 授賞式 15:45-16:45 第22回 LCA日本フォーラム表彰 記念講演 17:00-19:00 第22回懇親会 開催場所:海運クラブ 【住所:〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-4 海運ビル】 主 催:LCA日本フォーラム 後 援:経済産業省 / 日刊工業新聞社 |
||
| 【経済産業省 脱炭素成長型経済構造移行推進審議官賞】 | |||
| 「石油化学製品のLCIデータ更新」 | 一般社団法人プラスチック循環利用協会 調査研究部 部長 | 蟻川 英男 | |
| 【LCA日本フォーラム 会長賞】 | |||
| 「建設・不動産分野における温室効果ガス削減貢献量算定方法の素案提案」 | 株式会社日建設計 エンジニアリング部門 ダイレクター | 丹羽 勝巳 | |
| 「プラスチック・ガス化ケミカルリサイクルにおけるライフサイクル思考と循環型事業モデル構築への挑戦」 | 株式会社レゾナック 基礎化学品事業部 GX戦略推進部 プロフェッショナル | 別府 隆幸 | |
| 「ライフサイクル思考を取り入れたTNFD レポート第3 版の発行 ~拠点とバリューチェーンの水ストレス評価によるリスクスクリーニングの活用~」 |
日本電気株式会社 サプライチェーンサステナビリティ経営統括部 主任 | 蟹江 静香 | |
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|
| 2025.07.03 LCA日本フォーラム総会記念セミナー グリーンウォッシュにならないために |
<開催概要> 環環境経営への意識が高まるなか、産業界では自発的配慮の訴求だけでなく、ESG投資や情報開示などの枠組みなどによって投資家や消費者を含む社会に対して、より透明性のある環境負荷削減努力を明示することが企業に求められています。これら企業努力の成果を社会に発信することは近年注目を集め、環境配慮製品の普及や環境経営の充実につながると考えられる一方、過剰、誇張的な表現はグリーンウォッシュと指摘する声も高まってきています。 セミナーでは、グリーンウォッシュとはなにかについて200名を超える方々にご参加者いただき、近年の動向と事例を共有することができました。 開催日時:2025年 7月3日(木)14:40-17:00 開催場所:ハイブリッド 会場: 日比谷国際ビルコンファレンススクエア 8D オンライン配信: Zoomウェビナー 主 催:LCA日本フォーラム |
||
| 「【基調講演】 グリーンウォッシュへの対抗策としてのLCAへの期待」 | 環境省 大臣官房 地域脱炭素政策調整担当参事官 | 浜島 直子 | |
| 「グリーンウオッシュとは何か? ―The Great Greenwashing by John Pabonに見る考え方―」 | LCA日本フォーラム会長 | 稲葉 敦 | |
| 「GHGプロトコル、SBTi、CDP、RE100におけるグリーンウォッシュを防ぐ仕組みと進化の動向」 | 自然エネルギー財団 | 高瀬 香絵 | |
| 「化学製品のライフサイクル評価 ~住友化学の取組み~」 | 住友化学株式会社 | 林 真弓 | |
| 「鉄鋼業界の事例」 | 日本鉄鋼連盟 | 堂野前 等 | |
| 「ヤマト運輸のカーボンニュートラルに向けた取り組み」 | ヤマト運輸株式会社 | 倉橋 征示 | |
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|
| 2025.01.27 第21回 LCA日本フォーラム表彰 記念講演会 |
<開催概要> 令和7年1月27日(月)13時00分より、令和6年度「第21回LCA日本フォーラム表彰 表彰式・記念講演」が全国町村会館(東京千代田区)およびオンライン (記念講演のみ)にて開催されました。8件の受賞企業様および1名の功労者様に各賞の賞状および副賞が授与されました。 表彰式に引き続き、受賞者の表彰記念講演が行なわれ、フォーラム会員を中心に約90名の皆様にご参加頂き、盛況に開催されました。 開催日時:2025年1月27日(月) 13:00-14:25 第21回 LCA日本フォーラム表彰 表彰式 14:40-16:45 第21回 LCA日本フォーラム表彰 記念講演 17:00-19:00 懇親会 開催場所:全国町村会館 【住所:〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-35】 主 催:LCA日本フォーラム 後 援:経済産業省 / 日刊工業新聞社 |
||
| 「地域循環型アルミ産業網のグリーン化のためのDXプラットフォームの構築 ~とやまアルミバリューチェーンのCO2排出量の「見える化」と工程・企業間データ連携によるDXアプリケーション創出~」 |
公益財団法人富山県新世紀産業機構 | 村上 哲 | |
| 「ソフトウェア分野の脱炭素化に向けた業界連携活動」 | 日本電信電話株式会社 | 西澤 幸久 | |
| 「銅のサステナビリティ向上を目的とした、需要家と共創するリサイクル促進スキームの提案とLCA手法の活用」 | JX金属株式会社 ESG推進部 | 折笠 広典 | |
| 「電気銅のカーボンフットプリント算定・第三者クリティカルレビューの実施と、家電リサイクルLCA」 | 三菱マテリアル株式会社 金属事業カンパニー統括本部サステナビリティ推進部 | 小隅 誠司 | |
| 「レンタル可能な環境配慮型仮囲い『スライドパネル』によるライフサイクルCO2削減の取り組み」 | 株式会社ヤマトマネキン 常務取締役 | 古屋 健太郎 | |
| 「帝人フロンティアのLCAにおける取り組み」 | 帝人フロンティア株式会社 サステナビリティ戦略推進部 | 福永 右文 | |
| 「「MEGURU STATION®」を軸とした「MEGURU PLATFORM」の構築 | アミタホールディングス株式会社 取締役 兼 CGO | 岡田 健一 | |
| 「環境サステナビリティコンソーシアムにおけるCFP 分科会の取組」 | 長瀬産業株式会社 スペシャリティケミカル事業部 スペシャリティ第一部 環境ソリューション課 | 古川 翔一 | |
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|
| 2024.11.28 LCA日本フォーラム主催 秋季セミナー マスバランスモデルの利用とISO |
<開催概要> 2020年にISO 22095(Chain of custody ‐ General terminology and models)発行され、そこに示された5つのモデルの中の「マスバランスモデル」の産業界での利用が広がっています。ISO 22095:2020に示されたマスバランスモデルは、プロセスへのインプット材料が持つ情報を、アウトプット製品へ柔軟に配分することと理解することができますが、さらに詳細な算定方法がISO 13662として開発途上にあります。 また、マスバランスモデルのLCAでの利用方法を記述するISO14076が新しく提案されており、改訂中のISO14021 (自己宣言ラベル) でもその利用方法が議論されています。 本セミナーでは、ISO14077の提案者、Global Standards LeadのJulia Farber氏とISO13662の議長、Philippe Osset 氏をオンラインでお招きし、今後のマスバランスモデルについての見解を伺いました。フォーラム会員を中心に130名の方々にご参加いただき、盛況に開催されました。 開催日時:2024年11月28日(木)13:20-16:00 開催方式:オンライン配信: Zoomウェビナー 主 催:LCA日本フォーラム |
||
| 「開会挨拶:マスバランスモデルに関連するISOの作業状況」 | LCA日本フォーラム 会長 | 稲葉 敦 | |
| 「ISO/TC 308の活動」 | 一般財団法人日本規格協会 | 岡本 裕 | |
| 「鉄鋼業界でのchain of custodyモデルの利用」 | 一般社団法人日本鉄鋼連盟 | 堂野前 等 | |
| 「化学業界におけるマスバランスモデルの利用」 | 一般社団法人日本化学工業協会 | 藤井 宏行 | |
| 「ISO14077(マスバランスfor LCA)の提案(ビデオ)」 | Global Standards Lead | Julia Farber | |
| 「ISO13662(マスバランスの算定方法)とISO14077(マスバランスforLCA)」 | Philippe Osset | ||
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.06.17 令和6年度LCA日本フォーラム総会・総会記念セミナー |
<開催概要> 日本ではこれまで、企業の削減努力を削減貢献として主張する取組みが先駆的に進められてきました。 そして昨年、世界でもWBCSDが削減貢献量のガイダンスを公開するなど、脱炭素へのトランジッションとして、削減貢献量の活用が促されてきています。改めてこれから我が国がさらに政策面、金融面で削減貢献をどのように推し進めるのか、また様々な業界での削減貢献量の活用を共有いただき、フォーラム会員を中心に120名を超える方にご参加いただきました。 開催日時:2024年6月17日(月) 14:30-16:40 開催方式:ハイブリッド オンライン:Zoomウェビナー 会場:AP新橋 Dルーム [東京都港区新橋1-12-9] 主 催:LCA日本フォーラム |
|||
| 「【基調講演】経済産業省のLCA 施策の動向」 | 経済産業省 産業技術環境局 GX推進企画室 室長 | 荻野 洋平 | ||
| 「削減貢献量の金融機関における活用事例」 | 三井住友信託銀行株式会社 企業金融部 サステナブルファイナンスチーム チーム長 | 池田 篤朗 | ||
| 「ダイキン工業の削減貢献量の取組」 | ダイキン工業株式会社 東京支社渉外室(兼)CSR・地球環境センター 担当部長 | 小山 師真 | ||
| 「日立製作所の削減貢献量の取組」 | 株式会社日立製作所 環境戦略企画本部 企画室 部長代理 | 高江 瑞一 | ||
| 「日本ガス協会の削減貢献量のガイドライン」 | 一般社団法人日本ガス協会 企画部エネルギー・環境グループ マネジャー | 梶田 琢也 | ||
| 「メルカリの取引を通じて生まれた削減貢献量」 | 東京大学工学系研究科・都市工学専攻 特任研究員 | 文 多美 | ||
| 「質疑応答 ならびに まとめ(これからの削減貢献量・削減実績量)」 | 東京大学 | 醍醐 市朗 | ||
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|
| 2024.03.27 LCA日本フォーラム主催: CR2技術研究プロジェクト 公開シンポジウム |
<開催概要> LCA日本フォーラムでは、令和元年7月よりネガティブエミッション技術とカーボンリサイクル技術(Carbon Removal and Recycle Technologies;以下CR2技術)について、横断的にLCAの観点から研究して参りました。 今回の研究会は、これらの技術に関する背景、政策、そして実際に運用に挑んでいる事例をご紹介いただき、フォーラム会員様を中心に60名を超える方にご参加いただきました。 開催日時:2024年3月27日(水)13:00-15:00 開催方法:ハイブリッド 会場:AP新橋 Eルーム オンライン:zoomウェビナー 主 催:LCA日本フォーラム |
||
| 「地球気候の大崩壊が始まった!カーボンニュートラル、カーボンマイナスへ大転換を!!」 | 東京大学名誉教授 | 山本 良一 | |
| 「Carbon Dioxide Removal (CDR)の動向と市場創出に向けた検討状況」 | 経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 GX投資促進室 係長 | 山田 亮太 | |
| 「ガス化炉から生成されたバイオ炭の活用事例-南部町バイオマス発電所の事例-」 | 株式会社長大 事業推進本部・課長 | 竹下 光雄 | |
| 「(仮)DACスタートアップの挑戦」 | Planet Savers株式会社 取締役CSO | 伊與木 健太 | |
| 「ENEOS中央技術研究所におけるDAC実証について」 | ENEOS株式会社 中央技術研究所 先進技術研究所副所長 | 梶田 琢也 | |
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|
| 2024.02.28 LCA日本フォーラム主催: 国際動向セミナー |
<開催概要> 令和6年2月28日(水)14時00分より、「国際動向セミナー」がオンラインにて開催されました。 カーボンニュートラリティなど、LCAに関連する最新の環境政策および国際規格の動向について、各分野の専門家にご紹介いただきました。 本セミナーはフォーラム会員を中心に約120名の皆様にご参加頂き、盛況に開催されました。 開催日時:2024年2月28日(水) 開催場所:オンライン(Teams) 主 催:LCA日本フォーラム 共 催:日本LCA学会 |
||
| 「ISO14068-1」 | LCA日本フォーラム 会長 | 稲葉 敦 | |
| 「ISOのロンドン宣言とIWA42など」 | 一般財団法人 日本エネルギー経済研究所 | 工藤 拓毅 | |
| 「ISO/TC207(環境管理)規格開発動向」 | JEMAI | 星野 ちさと | |
| 「ISO/TC323(サーキュラーエコノミー)規格開発動向」 | JEMAI | 胡桃澤 昭夫 | |
| 「WBCSDの削減貢献量評価」 | 産業技術総合研究所 | 本下 晶晴 | |
| 「Panasonic GREEN IMPACT 「削減貢献量」の取り組みについて」 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 井口 敏祐 | |
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|
| 2024.01.23 第20回 LCA日本フォーラム表彰 記念講演会 |
<開催概要> 令和6年1月23日(火)13時00分より、令和5年度「第20回LCA日本フォー ラ ム表彰 表彰式・記念講演」が全国町村会館(東京千代田区)およびオンライン (記念講演のみ)にて開催されました。5件の受賞企業様および2名の功 労者様に 各賞の賞状および副賞が授与されました。 表彰式に引き続き、受賞者の表彰記念講演が行なわれ、フォーラム会員を中 心 に約80名の皆様にご参加頂き、盛況に開催されました。 開催日時:2024年1月23日(火) 13:00-14:25 第20回 LCA日本フォーラム表彰 表彰式 14:40-16:25 第20回 LCA日本フォーラム表彰 記念講演 開催場所:【一般参加者】オンライン(Zoom)※記念講演のみ 【受賞者、関係者、その他】会場:全国町村会館 主 催:LCA日本フォーラム 後 援:経済産業省 / 日刊工業新聞社 |
||
| 「化学産業における製品カーボンフットプリント算定推進~ガイドラインの策定と算定システムの開発・展開~」 | 一般社団法人 日本化学工業協会 技術部 部長 | 藤井 宏行 | |
| 住友化学株式会社 レスポンシブルケア部 主席部員 | 林 真弓 | ||
| 「デジタル技術を活用した企業間でデータ連携によるサプライチェーンCO2 排出量の「見える化」への取り組み」 | Green x Digital コンソーシアム 見える化WG 主査 | 稲垣 孝一 | |
| 「再生樹脂の原単位算定と製品LCAへの活用」 | 株式会社リコー ESG戦略部 ESGセンター ESG推進室 RBグループ | 田中 涼 | |
| 「CFP 算定ツールの開発および企業のCFP 算定支援等 LCA 算定普及に貢献した活動」 |
株式会社ゼロボード セールス&マーケティング本部営業部長 | 飯田 啓之 | |
| 「LCA を活用した気候/自然関連リスク分析 ― TCFD/TNFD レポートへの応用」 |
株式会社資生堂 シニアスペシャリスト | 大橋 憲司 | |
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.06.28 産業のCFP |
<開催概要> カーボンニュートラルの実現にむけて炭素排出量を定量化する重要度が増しているなか、排出量の算定ルールやガイドラインを求める声が高まっています。これを受けて、各産業界では算定ルールやガイドラインの取りまとめが進んでいます。そこで、本セミナーでは、先駆的に算定ルールやガイドラインを策定した業界を紹介しました。おかげさまで、オンライン、会場あわせて約160名の皆様にご参加いただき、盛況な会となりました。 開催日時:2023年6月28日(水) 14:15-16:50 開催場所:ハイブリッド 主 催:LCA日本フォーラム |
||||||
| 「カーボンフットプリントと経済産業省の取組」 | 経済産業省 産業技術環境局 環境経済室 企画官 | 内野 泰明 | |||||
| 「国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)における自動車LCAの動向」 | 国土交通省 自動車局 車両基準・国際課 国際企画室長 | 佐藤 健二 | |||||
| 「アパレル業界のHigg Indexのガイドライン」 | 東レ株式会社 繊維GR・LI事業推進室 主席部員 | 本田 圭介 |
|||||
| 「化学産業におけるCFP算定ガイドライン」 | 一般社団法人日本化学工業協会 技術部 部長 | 小西 章夫 | |||||
| 「日本自動車部品工業会の算定ガイドライン」 | 一般社団法人 日本自動車部品工業会 | 棚橋 昭 | |||||
| 「化粧品業界におけるLCA算定手法の標準化」 | 株式会社資生堂 経営革新本部 サステナビリティ戦略推進部 | 大橋 憲司 | |||||
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.03.31 Carbon Removal & Recycle (CR2)のLCA 算定WG 報告会 |
<開催概要> LCA 日本フォーラムでは、2018 年にネガティブエミッション技術に関する研究会を立ち上げ、以来ネガティブエミッション技術やカーボンリサイクル技術に関するLCA 評価を検討して参りました。 2021年にLCA ガイドラインを策定し、このLCA ガイドラインに基づいて、様々なCR2技術のLCA算定を実施しています。特に今年度は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が実施している「ムーンショット型研究開発事業」の「温室効果ガスを回収、資源転換、無害化する技術の開発」プロジェクトと共にLCAの算定を進めました。ここでの成果を皆様と共有するとともに、算定をとおして議論された新技術におけるLCA 評価の考えかたなどをご紹介しました。フォーラム会員を中心に多くの方々にご参加頂き、盛況に開催されました。 開催日時:2023年3月31日(金)13:00-14:30 開催場所:オンライン(Teams) 主 催:LCA日本フォーラム/一般社団法人産業環境管理協会 共 催:化学工学会CCUS 検討委員会 |
|||
| 「大気中からの高効率CO2 分離回収・炭素循環技術の開発のLCA」 | 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 余語 克則 | ||
| 「電気化学プロセスを主体とする革新的 CO2 大量資源化システムの LCA」 | 国立大学法人東京大学 | 杉山 正和 | ||
| 「C4S 研究開発プロジェクトのLCA」 | 国立大学法人東京大学 | 野口 貴文 |
||
| 「冷熱を利用した大気中二酸化炭素・直接回収(Cryo-DAC®)のLCA」 | 国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 | 則永 行庸 | ||
| 「“ビヨンド・ゼロ”社会実現に向けたCO2 循環システムの研究開発のLCA」 | 国立大学法人九州大学 | アンドリュー チャップマン | ||
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.02.27 非財務情報の開示:TNFD と生物多様性評価 |
<開催概要> TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures;自然関連財務情報開示タスクフォース)が2021 年に発足し、現在フレームワークの策定が進められています。気候変動への対応が優先されることが多いなか、今後は、金融機関や企業が自然資本に関するリスクや機会を評価し、開示することが求められていくことでしょう。LCA 日本フォーラムでは、この急速に高まりつつある自然資本への関心を受け、皆様のTNFD に関するより一層深い理解と、今後の環境経営対策や自然資本評価計画の一助となるように、本セミナーを企画いたしました。フォーラム会員を中心に約170名の皆様にご参加頂き、盛況に開催されました。 開催日時:2023年2月27日(月)14:00-16:15 開催場所:オンライン(Zoomウェビナー) 主 催:LCA日本フォーラム |
|||
| 「基調講演①: TNFD と環境省の取組」 | 環境省 自然環境局 自然環境計画課 生物多様性主流化室 室長補佐 | 朽網 道徳 | ||
| 「基調講演②: 生物多様性とサステナビリティ経営」 | 株式会社レスポンスアビリティ 代表取締役/JBIB 理事・事務局長 | 足立 直樹 | ||
| 「TNFD への参加:TNFD 開示勧告草案について」 | MS&AD インシュアランス グループ ホールディングス | 原口 真 |
||
| 「TNFD LEAP アプローチを使った自然資本評価」 | キリンホールディングス株式会社 CSV戦略部 | 小此木 陽子 | ||
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.02.01 第19回 LCA日本フォーラム表彰 記念講演会 |
<開催概要> 2023年2月1日(水)13時00分より、令和4年度「第19回LCA日本フォーラム表彰 表彰式・記念講演」が都市センターホテル(東京千代田区)およびオンライン(記念講演のみ)にて開催され、7件の受賞企業様および1名の功労者様に各賞の賞状および副賞が授与されました。 表彰式に引き続き、受賞者の表彰記念講演が行なわれ、フォーラム会員を中心に約90名の皆様にご参加頂き、盛況に開催されました。 開催日時:2023年2月1日(水) 13:00-14:15 第19回 LCA日本フォーラム表彰 表彰式 14:30-16:30 第19回 LCA日本フォーラム表彰 記念講演 開催場所:【一般参加者】オンライン(Zoom)※記念講演のみ 【受賞者、関係者、その他】会場:都市センターホテル 主 催:LCA日本フォーラム 後 援:経済産業省 / 日刊工業新聞社 |
|||
| 「凸版印刷の環境影響評価と環境活動 〜国内、海外一体とした2050年環境ビジョン~」 |
凸版印刷株式会社 製造統括本部 エコロジーセンター | 松井 初音 | ||
| 「DNP ライフサイクル CO2認証システムの構築」 | 大日本印刷株式会社 Lifeデザイン事業部イノベーティブ・パッケージングセンター ビジネスデザイン本部環境ビジネス推進部第2グループ | 濱田 倫 | ||
| 「ライフサイクルCO2排出量の算定・評価により、製品の販促・改善を目指すSF6ガスフリーエコタンク形VCB」 | 株式会社 明電舎 経営企画本部 サステナビリティ推進部 支配人 | 村越 弥之 | ||
| 「鉱山機械部品の新品ならびに再生品における環境影響の見える化」 | 日立建機株式会社 再生事業部 サーキュラーエコノミー推進部 技術開発 Gr 主任 | 金澤 智尚 | ||
| 「鉄鋼のLCAに関する広報活動」 | 一般社団法人日本鉄鋼連盟 技術政策委員会 企画委員会 座長 | 礒原 豊司雄 | ||
| 「サプライチェーンGHG排出量の管理及び削減に向けた取り組み」 | 九州電力株式会社 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部(環境) 部長 | 江口 洋之 | ||
| 「画像ベースインフラ構造物点検サービスの削減貢献量算定」 | キヤノン株式会社 LCA・環境技術課 専任主任 | 花本 英俊 | ||
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|
| 2023.01.23 国際動向セミナー |
<開催概要> 今年度のLCA日本フォーラムの国際動向セミナーでは、カーボンニュートラルや資源循環など、LCAに関連する最新の環境政策および国際規格の動向について、各分野の専門家にご紹介いただくとともに、今後の環境対策について議論しました。 本セミナーはフォーラム会員を中心に約190名の皆様にご参加頂き、盛況に開催されました。 開催日時:2023年1月23日(月)14:00-16:50 開催場所:オンライン(teamsウェビナー) 主 催:LCA日本フォーラム 共 催:日本LCA 学会 |
||
| 「カーボンフットプリントに関する政策動向」 | 経済産業省 産業技術環境局 環境経済室 企画官 | 内野 泰明 | |
| 「ISO TC323について」 | 東京大学 大学院工学系研究科 | 梅田 靖 | |
| 「TC323 とTC207/SC5 のJointWG14の動向について」 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 環境・エネルギーユニット/持続可能社会部 | 村中 潤 (一般社団法人循環経済協会) |
|
| 「ISOにおけるGHG算定・報告関連規格検討動向 ISO 14068/IWA 42/14064-1改定の相互関係」 | 一般財団法人 日本エネルギー経済研究所 | 工藤 拓毅 | |
| 「TC207/SC7:ISO14083(輸送のISO)」 | ヤマト運輸株式会社 社長室 戦略渉外グループ | 星 雄一朗 | |
| 「TC207/SC5:ISO14075(ソーシャルLCA)」 | Climate Solutions Director / Persefoni Japan G.K. | 高野 惇 | |
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.09.29 座談会 - WBCSDのPathfinder Framework : Guidance for the Accounting and Exchange of Product Life Cycle Emissions と LCA |
<開催概要> 脱炭素への動きが加速するなか、全体の二酸化炭素排出量の約80%を占めると言われるSCOPE3における実質の排出量を把握するチャレンジが始まっています。 WBCSDは、昨年「Pathfinder Framework: Guidance for the Accounting and Exchange of Product Life Cycle Emissions」を公開しました。これを契機に、より精緻で確実な1次データによるLCAを簡単かつ安全に実施する方法が模索され始めています。 LCA手法は今、時代とともに進化しようとしています。 これからのLCAがどのように変革していくのか、皆様と考える機会になればと思い企画いたしました。 本セミナーはフォーラム会員を中心に約90名の皆様にご参加頂き、盛況に開催されました。 開催日時:2022年9月29日(木)18:00-19:00 開催場所:オンライン(Zoom) 主 催:LCA日本フォーラム |
|||
| 「About Pathfinder Framework」 | Anna Stanley, Director, | Climate Action & Member of the Extended Leadership Group, WBCSD | ||
| 「LCA details of the Framework: Pilot studies and its application in practice」 | Cecilia Valeri, Manager, | Climate Taxonomy, WBCSD | ||
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.07.26 「LCAインベントリデータ、サプライチェーンデータ活用の動向と課題 |
<開催概要> 本セミナーでは、「ライフサイクルイン ベントリデータ及びそのデータベース」の国内外動向や課題、今後の新たな展開としての「サプライチェーンデータ活用」の最新動向をフォローし、改めてLCA評価やGHG排出量及びCFP算定における「データ」に焦点を当てました。そして、中長期のカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー等の持続可能な社会実現への取組みとして、サプライチェーンやバリューチェーンのあらゆる産業にとって共通且つ協力・連携すべき課題を各工業会関係者へも提起しつつ、認識の共有を図りました。 本セミナーはフォーラム会員を中心に約160名以上の皆様にご参加頂き、盛況に開催されました。 開催日時:2022年7月26日(火)13:00-17:00 開催場所:オンライン(Teamsウェビナー)※予定 主 催:LCA日本フォーラム |
|||
| 「気候変動に関する国内外の動向とGXリーグにおける取組」 | 経済産業省 産業技術環境局環境経済室 | 中山 竜太郎 | ||
| 「ライフサイクルインベントリデータベースの国際ネットワーク化の現状と課題 ~グローバルLCAデータアクセスネットワーク(GLAD)及び関連動向」 |
TCO2株式会社 | 正畠 宏一 | ||
| 「ライフサイクルインベントリデータベースの開発と課題 ~インベントリデータベースIDEAの開発及び関連動向」 | 産業総合技術研究所 | 田原 聖隆 | ||
| 「鉄鋼産業におけるLCIデータベース開発の取組み」 | 日本鉄鋼連盟/日本製鉄株式会社 | 礒原 豊司雄 | ||
| 「電子部品業界のLCAへの取組み」 | JEITA電子部品/TDK株式会社 | 横山 亮 | ||
| 「機能樹脂製品における製品別カーボンフットプリントデータの提供」 | 旭化成株式会社 | 崎田 雄大 | ||
| 「サプライチェーンCO2排出量「見える化」のアプローチ」 | グリーン×デジタルコンソーシアム/日本電気株式会社 | 稲垣 孝一 | ||
| 「自動車業界におけるLCAの取組と課題」 | 一般社団法人日本自動車工業会/本田技研工業株式会社 | 田伏 功 | ||
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|
| 2022.06.15 「プラスチックリサイクルを考える」研究会 成果報告会 |
<開催概要> LCA日本フォーラムの会員様を対象に、令和元年6月から「プラスチックのリサイクルを考える」を開催しております。本セミナーでは,参加企業様の評価事例を紹介していただくとともに、この研究会で2年間にわたって議論してきた内容をもとに,プラスチック資源循環によるCO2排出の削減効果をLCAによって評価するための課題を整理します。 開催日時:2022年6月15日(水)14:15~17:00 開催場所:オンライン(Zoomウェビナー) 主 催:LCA日本フォーラム 共 催:CLOMA |
||
| 「プラスチック資源循環のLCAの枠組みと論点」 | 東京大学 | 中谷 隼 | |
| 「バイオマスプラスチックとポリカーボネートの比較」 | 日本電気株式会社 | 田中 修吉 | |
| 「原料PPを化石資源由来からバイオマス由来に変更」 | 東罐興業株式会社 | 角田 浩太郎 | |
| 「廃プラスチックを利用したセメント生産の評価」 | 太平洋セメント株式会社 | 杉澤 建 | |
| 「廃プラ油化リサイクルのLCA検討」 | ENEOSホールディングス株式会社 | 小倉 俊 | |
| 「再生プラスチック原料を使用したインフラ製品評価」 | 積水化学工業株式会社 | 三浦 仁美 | |
| 「ペットボトルのモノマーリサイクルの評価」 | 株式会社JEPLAN | 石津 縁 | |
| 「ケミカルリサイクルによるオレフィン製造の評価」 | 昭和電工株式会社 | 宮武 正人 | |
| 「モノマテリアル包材によるリサイクル性向上の評価」 | 大日本印刷株式会社 | 濱田 倫 | |
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|
| 2022.03.16 Carbon Removal & Recycle (CR2)のLCA算定WG 報告会 |
<開催概要> LCA日本フォーラムでは、2018年よりカーボンリムーバルとリサイクル技術(CR2)に関する研究会を開催しており、2021年には、LCAガイドラインを策定いたしました。今年度は、このLCAガイドラインに基づいて、5つのCR2技術のLCA算定を実施しました。これらCR2技術のLCA評価の結果を参加者の皆様と共有するとともに、算定をとおして浮彫となったガイドラインの課題やLCA評価自体における考えかたの整理について議論いただきました。約110名の皆様にご参加いただき、盛況に開催されました。 開催日時:2022年3月16日(水)14:00-16:00 開催場所:オンライン(Zoomウェビナー) 主 催:LCA日本フォーラム/一般社団法人産業環境管理協会 共 催:化学工学会CCUS研究会 ※本セミナーは一部、経団連 環境対策推進財団助成事業の助成金で開催しております。 |
||
| 「LCA算定事例① BECCS」 | 信州大学 繊維学部 教授 | 高橋 伸英 | |
| 「LCA算定事例② 低炭素型炭酸化養生コンクリート製品」 | 太平洋セメント株式会社 カーボンニュートラル技術開発プロジェクトチーム | 星野 清一 | |
| 「LCA算定事例③ バイオ炭」 | 立命館大学 政策科学部 准教授 | 中野 勝行 | |
| 「LCA算定事例④ ブルーカーボン」 | 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 沿岸環境研究グループ長 | 桑江 朝比呂 | |
| 「LCA算定事例⑤ 風化促進」 | 早稲田大学 創造理工学部 教授 | 中垣 隆雄 | |
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|
| 2021.01.28 第18回 LCA日本フォーラム表彰 表彰式及び記念講演 |
<開催概要> 2021年1月28日(金)13時30分より、令和3年度「第18回LCA日本フォーラム表彰 表彰式・記念講演」が大手町サンケイプラザ(東京千代田区)およびオンラインにて開催され、6件の受賞企業様および1名の功労者様に各賞の賞状および副賞が授与されました。 表彰式に引き続き、受賞者の表彰記念講演が行なわれ、フォーラム会員を中心に80名以上の皆様にご参加頂き、盛況に開催されました。 開催日時:2021年1月28日(金) 13:30-14:40 第18回 LCA日本フォーラム表彰 表彰式 14:50-16:30 第18回 LCA日本フォーラム表彰 記念講演 開催場所:【一般参加者】オンライン(Zoom/youtube) 【受賞者、関係者、その他】会場:大手町サンケイプラザ 主 催:LCA日本フォーラム 後 援:経済産業省 / 日刊工業新聞社 |
||
| 「全国百貨店会員店舗を対象にしたSCOPE3の実施」 | 一般社団法人 日本百貨店協会 政策グループ主幹 | 高橋 亜子 | |
| 「タイヤのLCCO2算定ガイドラインVer2.0を活用した国内市場に於けるCO2排出量削減効果の公表、及びガイドラインVer3.0の作成」 | 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会 環境部会 部会長 株式会社ブリヂストン Gサステナビリティ部門主幹 |
森永 啓詩 | |
| 「籾殻を原料、燃料とした、無機保温材の開発 当該製品のライフサイクルCO2排出量等の定量化活動 当該開発を契機とした社内啓発活動」 |
日本インシュレーション株式会社 管理本部経営企画部 取締役部長 | 金子 一郎 | |
| 「飼料添加物DL-メチオニンの環境貢献」 | 住友化学株式会社 レスポンシブルケア部 主席部員 | 林 真弓 | |
| 「インドネシアの工場におけるオンサイト型排水処理システムのLIME3によるLCA評価」 | 株式会社新菱 経営企画本部 カーボンニュートラル室 課長代理 | 金子 愛里 | |
| 「GHG削減貢献量評価手法の確立および普及」 | 東京大学先端科学技術研究センター 准教授 | 醍醐 市朗 | |
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|
| 2021.12/9 LCA日本フォーラム 国際動向セミナー |
<開催概要> 先日閉幕したCOP26では、段階的石炭火力発電の削減なども成果文書に盛り込まれ、一1.5℃目標へ向けて世界の脱炭素への潮流は加速する一方です。本セミナーでは、そのCOP26の様子および最新の政策や国際規格の開発状況について、各分野の専門家の皆様にご紹介いただきました。参加者は約170名にのぼり、盛況に開催されました。 開催日時:令和3年12月9日(木) 14:00-16:30 開催形式:オンライン(Zoomウェビナー配信) 主 催:LCA日本フォーラム 共 催:日本LCA学会 |
||
| 「COP26報告:世界が1.5℃目標へ、パリ協定が示す脱炭素化の道筋」 | WWFジャパン 気候・エネルギーグループ オフィサー(非国家アクター連携担当) | 田中 健 | |
| 「カーボンプライシングの方向性」 | 経済産業省 環境経済室 | 荒井 次郎 | |
| 「ISO/TC207/SC7(GHGおよび関連する活動)/ISO14068(カーボンニュートラリテイ)の動向 」 | 日本エネルギー経済研究所 | 工藤 拓毅 | |
| 「ISO/WD14075 ソーシャルLCA(S-LCA)」 | 日本LCA推進機構 | 稲葉 敦 | |
| 「ISO/TC323(サーキュラーエコノミー)の動向」 | 東北大学名誉教授 | 中村 崇 | |
| 「サステナブルファイナンスと情報開示」 | 東京理科大学 | 加藤 晃 | |
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|
| 2021.10/19 気候行動計画立案支援プロジェクトセミナー: カーボンニュートラルへの自治体の活動 |
<開催概要> LCA日本フォーラムは、地方自治体の気候行動計画の策定を支援することを目的として、昨年度「気候行動計画立案支援プロジェクト」設立しました。 本セミナーは、その活動の一つとして、公共団体の脱炭素に関する最新動向をご紹介頂きました。 約100名の皆様にご参加いただき、盛況に開催されました。 開催日時:令和3年10月19日(火) 14:00-16:30 開催形式:オンライン(Zoom) 主 催:LCA日本フォーラム |
||
| 「特別講演:地域脱炭素の取組について」 | 環境省環境計画課 課長 | 松田 尚之 | |
| 「ゼロカーボンシティ実現のための新たな発想での計画づくり」 | 芝浦工業大学 | 中口 毅博 | |
| 「カーボンニュートラルシミュレーターを活用した地方自治体での脱炭素政策の検討」 | 千葉大学 | 倉阪 秀史 | |
| 「脱炭素・未来ワークショップで地域脱炭素を考える」 | 芝浦工業大学 | 栗島 英明 | |
| 「招待講演:2050ゼロカーボンに向けた長野県の取組」 | 長野県 環境部環境政策課 課長 | 真関 隆 | |
| 「産学公の共創に基づく地域におけるLCAの活用」 | 東京大学 | 菊池 康紀 | |
| 講演題目 | 講演者所属 | 講演者 | |
|---|---|---|---|
| 2021.07.02 LCA日本フォーラム/ 令和3年度LCA日本フォーラム総会セミナー GHG削減貢献量算定研究会中間報告会と削減貢献量算定の動向 |
<開催概要> LCA日本フォーラムでは、企業の皆様に削減貢献量算定をさらに活用していただくために「GHG削減貢献量算定研究会」を令和元年12月より開催しております。 総会セミナーでは、カーボンニュートラリティや国際規格などの国際的な枠組みのなかでその役割が広がりつつあるGHG削減貢献量算定についてこの研究会での取組の中間報告をするとともに議論いただきました。 約170名の皆様にご参加いただき、盛況に開催されました。 開催日時:2021年7月2日(金)14:00ー16:45 開催形式:オンライン(Zoom) 主 催:LCA日本フォーラム |
||
| 「削減貢献量とは」 | 東京大学 先端科学技術研究センター | 醍醐 市朗 | |
| 「削減貢献量の国内外におけるガイドライン等」 | 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 | 本下 晶晴 | |
| 「招待講演:気候変動、削減貢献に関する経団連の取組み」 | 日本経済団体連合会 環境エネルギー本部長 | 長谷川 雅巳 | |
| 「解説:IEC/TC111 GHG削減貢献量算定等国際規格開発の取組み」 | IEC/TC111/WG17 Convenor 蛭田 貴子(シュナイダーエレクトリック)
同 Secretary 齋藤 潔(日本電機工業会) |
||
| 「解説:ISO/WD14068(カーボンニュートラリテイ)と削減貢献量」 | 日本LCA推進機構 | 稲葉 敦 | |
| 「各社の取組紹介:キヤノンの取組み」 | キヤノン株式会社 | 花本 英俊 | |
| 「各社の取組紹介:日本自動車部品工業会の取り組み」 | 株式会社デンソー | 棚橋 昭 | |
| 「各社の取組紹介:三菱電機の取組み」 | 三菱電機株式会社 | 前田 智佐子 | |
- 会員専門ページ
-
1. LCAデータベース2. 講演資料閲覧
- セミナー情報
- 最新セミナー情報
- 25周年記念式典
- 20周年記念シンポジウム
- 過去のセミナー一覧