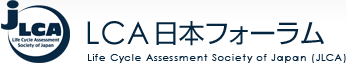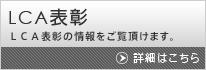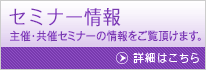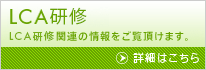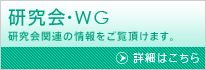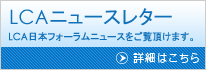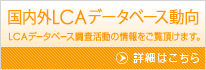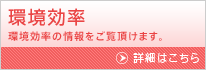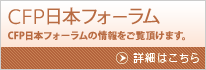- HOME
- > 設立30周年
設立30周年
LCA日本フォーラム30周年によせて
 |
1995年にLCA日本フォーラムが設立されて30年になります。このフォーラムは、1993年に設置されたISO/TC207:環境マネジメント技術委員会、その中でも特にSC5:ライフサイクルアセスメント(LCA)分科会に対応する産官学の協働プラットフォームとして設立されました。1992年は「持続可能な発展」が世界の共通認識となった「UNCED(環境と開発に関する国際連合会議)」がリオデジャネイロで開催された年であり、この頃に「公害」から「地球環境」に大きく枠組みが変わったと考えることができます。 このフォーラムは、経済団体連合会評議会副議長である関本忠弘氏を会長とする67名の委員と、東京大学生産技術研究所教授山本良一氏を幹事長とする24名の幹事、及び述べ120余名の専門部会を擁し、海外でのLCA活動をキャッチアップし、国内の産業に展開する、まさに国家規模の活動を開始しました。その成果が、1997年6月に「LCA日本フォーラム報告書」としてまとめられ、そこでの提言を基に、1998年度から6か年に渡るいわゆる「LCA国家プロジェクト」が開始されました。 国家プロジェクトの当初は、52の工業会による代表製品のLCAデータの収集とその平均値の公表を目的としました。この活動により、LCAの方法が産業界に行き渡ることになりました。また、当時の通商産業省資源環境技術総合研究所により、日本独自の環境影響評価手法(LIME)が開発されました。多くの企業が環境報告書に代表製品のLCA結果を掲載しました。これを私は、わが国におけるLCA活動の「第一の波」と位置付けています。 「第二の波」は、英国が2006年に始め、これを受けて2009年~2011年に経済産業省が環境省及び農林水産省と協働で「試行プロジェクト」を行ったカーボンフットプリント(CFP: Carbon Footprint of Products)です。このプロジェクトでは、スーパーマーケットで販売されている食品や日用品にLCAで計算されたGHG排出量を表示することが試行されました。いわゆる「CO2の見える化」です。 現在の第三の波は、国際的に2015年のSDGsとパリ協定で始まったカーボンニュートラルの波です。日本では政府の2030年までのGHGの46%削減(2013年度比)と、2050年に達成するカーボンニュートラル宣言で加速されています。第二の波であったCFPは「製品」を対象としていましたが、現在のカーボンニュートラルは主として「組織」を対象としています。ISO14068-1:2023(カーボンニュートラリテイ)が発行され、ISO14060(ネットゼロに向かう組織)が発行に向けて作業中です。 第二の波と第三の波は気候変動に着目する活動ですが、LCAは気候変動だけでなく、様々な環境影響を評価する方法として開発されてきました。最近ではISO14075:2024(ソーシャルLCA)も発行されました。今後、気候変動を超えた幅広い活動に展開されると思われます。今後もLCAフォーラムの活動をご支援いただけますようお願い申し上げます。 LCA日本フォーラム会長 稲葉 敦 |
30周年記念祝賀会
【開催概要】
| 開催日時: | 令和7年 11月6日(木) |
|---|---|
| 開催場所: | 如水会館 松風の間 |
| 主催: | LCA日本フォーラム |
【式次第】
| 1 開式挨拶 |
LCA日本フォーラム会長 稲葉 敦 |
|---|---|
| 2 来賓挨拶 |
経済産業省 イノベーション・環境局GXグループ 脱炭素成長型経済構造移行推進審議官 伊藤 禎則 様 |
|
日本経済団体連合会 副会長・事務総長 久保田 政一 様 |
|
|
東京大学 名誉教授(前LCA日本フォーラム会長) 山本 良一 様 |
|
| 3 乾杯 |
産業技術総合研究所/LCA日本フォーラム運営委員長 玄地 裕 |
| 4 中締め |
日本製鉄株式会社/LCA日本フォーラム副会長 船越 弘文 様(代読 堂野前 等 様) |
| 5 閉会挨拶 |
早稲田大学/LCA日本フォーラム情報企画委員長 伊坪 徳宏 |
| 6 閉会 | |
【祝賀会の様子】